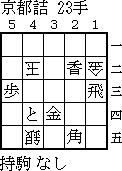
京都詰は、将棋パズル誌
この将棋は田宮克哉さん考案
他人がやっていないジャンルなので、自分が作ったものが即ちその分野の歴史となる。余詰を除いて19局発表したが、そのうち13局が京都煙である。
煙とはいえ、所詮駒がたった10枚のミニ将棋のこと、発展性や妙手は望むべくもないが、狭い中で精一杯バラエティを付けるよう努力してきた。
第1号の京都双玉煙『煙草』
たかが23手、とはいえ、京都将棋を少し指してみると分かるが駒の動きは不自由で、合駒は入れにくく、連続の捌きは非常に難しい。
30手を目標とし、ついに達成できなかったが、25角の3段活用が最大限の主張である。今後記録に挑戦する人があるとも思えないが、できるとすればこの銀/角をいかに活用するかがカギになることだろう。
最初は田宮さんが詰パラ誌上の1コーナーとして連載していたもので、将棋の駒を使ったオリジナルパズルを出題、解答募集されていた。後に独立してミニコミ誌となり、他誌でやっていない詰物を専門に扱う、投稿者が出題・解答集計・結果稿作成をするので発行者も解答参加する、作品が溜まると作品集を作る、など、ユニークな運営が特色であった。
田宮さんは「将棋パズル」の解答賞品に、オリジナルパズルを満載した「どたまのトレーニング資料(どたトレ資料)」なるものを多数製作されている。その一環として、これまた独特のミニ将棋を紹介した資料を発行されているが、そのうちもっとも世間に広まったのが京都将棋である。
使用駒の名称と裏表の関係(香−と、銀−角、金−桂、飛−歩)、さらに指し将棋の駒を並べる順番をも表現している。
田宮さんの主張によれば、「京都詰め」と書くのが正しい。「京都詰」だと「キョウトキツ」と読む。
| 『煙草』 |
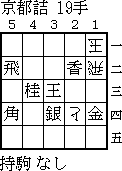 |
2枚の飛車捨てから収束がいかにも京都詰らしい手順。
| 『曲球』 |
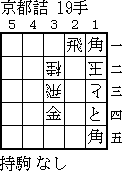 |
6手目13と、と打つと初形に戻るようだが、この時は24金/桂が成立する。よって33飛の移動合が最善。
| 『前進』 |
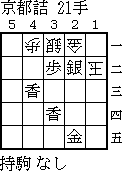 |
33香/とから45桂に至る手順が京都詰としては異色。
| 『流星』 |
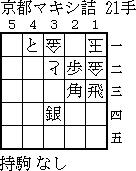 |
マキシでは当然とはいえ、右辺の駒を全部捨てて45銀/角がちょっと意表を突くと思う。
ボカスカ将棋
最初は詰物に馴染まないと思っていたが、手がけてみると意外に趣向の宝庫であることが分かってきた。
二枚金による追い趣向は佐藤伸夫さんが初めて作品化されたが、もっといろいろなバリエーションが可能だろうと思っていたとき、別途考えていた「銀2枚を持っての7段目の馬の横追い」をうまく結び付けることができて、作品になると思ったのを憶えている。
題名はそのような成立事情を表現したもの。
最初左上には駒を置かず、二枚銀で追いつめて終わりだったが、趣向を徹底するために二枚金での引き戻しを入れて、起承転結が明快な完成品になった
ところで本局、最初の発表時も改良図を出したときも不完全指摘はなかったが、初形玉の近くに強力な馬がいるため、いまだに余詰を恐れている。
離し王手に対するボカスカの強烈な守備力
ボカスカは大味なところもあるが、まだまだ未発掘の宝の山だと思う。
ボカスカ将棋の棋譜は、2枚以上同時に動く場合は、将棋パズル誌では矢印で表現していたが、本書では右・下・右上・左下など方向を表わす語と駒名称とを組み合わせて表現する。方向はすべて先手から見た向き。成るときは成る駒の座標のみ(xy,…)成、などと書く。
発表時は左上に駒が残ったが、後年収束を改良して煙になった。
たとえば金4枚を固めて打つ!
「寝済の花嫁」とは、佐藤伸夫さんの考案になるもので、独自の進化を遂げた「将棋パズル」誌でなければ生まれなかったであろう奇抜なルール。
もともとネズミ年の年賀作品用の単発ルールだったが、これまた意外に趣向向きのようで、他の人も作品を発表するようになったため、一つのジャンルとして認知されるようになった。
ほとんど世に知られていないがこのルールでの小駒煙
本作は、当初軽い追い趣向を目指して作り、53のと金は、はじめは歩だった。ところが42に捨てる余地を作ることで趣向の流れから自然に紛れ筋に陥りやすいと気づいたのが投稿直前。
もちろん42から作意同様に追うと姫が97に逃げ込んで成ってしまうので詰まない。
はまった解答者は少なかったが、作意解答者からは好意を持って迎えられた。
姫の行動範囲が制限されていることを除けば、一種の条件付き非対称駒
花沢正純作
駒固有の利き筋が左右非対称であるのは、禽将棋における鶉くらいのものであろう。田宮さん考案の「漢字駒」と称する駒群にも非対称のものが多数存在するが、パズル向けのみで指し将棋や詰物には現れていない。
おまえが闇に葬ったんじゃないか、という声には沈黙するしかない。
「フェアリー駒の右京」ということになっているが、実はフェアリー駒詰でこれといった作品がない。OFMにいくつか発表作はあるが、あるものはあまりにマニアックで難解なため、解こうと言う人はいないだろう(ナイトライダー玉
程よい難解性と手順のバランスが取れているのは本作くらいである。
神無一族に加入し、fmを使用するようになってはじめてのまともな作。前三局と比べて作風がまるで違っているのがお分かりだろう
同じフェアリー駒作品でも、パラ97年8月号に発表した獅子玉ばか詰
ナイト系の駒詰はコンパクトな形で空き王手を表現しやすい。それを8手で2回行って詰上りを見えにくくしている。飛打ちと空き王手のセットで繰り返し手順になっているのも取り柄だろう。収束の形から純粋に逆算で双裸玉にできたのは奇跡的といえる。
ところで本局のような双裸玉は、近い将来コンピュータにより全検されて無数の完全作リストの1局として埋もれてしまう宿命にある。
つまりこの種の作品は、いかに創意を盛り込もうともいまや創作物の性格が薄れつつあるのだ。
これをフェアリーの崩壊の危機と捉える向きもあるが詰将棋の基盤にしっかりと根づいたフェアリー詰将棋はもはやそんな脆弱なものではない。
無限に発展する潜在力を秘めた進化の過程なのだと受け取りたい。
本作はその進化の過程で、かろうじて私の創作の記録をとどめた記念碑のひとつと言えるであろうか。
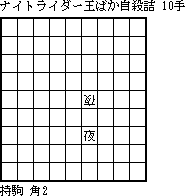 |
夜(ナイトライダー): ナイトの利き方向に走る駒。たとえば11夜の利きは 23、35、47、59、32、53、74、95の10箇所。
詰上りから強引に双裸玉にしたもの。
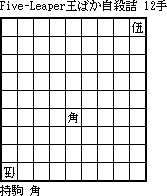 |
伍(Five-Leaper): タテヨコ1マスの長さを1としたとき、ちょうど5の距離に利きを持つ駒。たとえば11伍の利きは、16、45、54、61にある。
56角がないと、11-99のラインに対する対称解も成立する。
マイナーなルールである点では共通しているが。
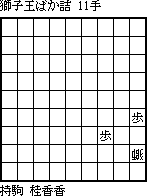 |
獅(獅子):中将棋の駒で、2手指しができる王の性能を持つ。2つの駒を連続して取ることもできるし、すぐとなりにある駒は取って元の位置に戻ることもできる(いわゆる「居喰い」)。11にいる獅子が22の駒を取って23へ行く時は、「22-23獅」と表記する。
最大24箇所に利きを持つ獅子玉で、手順を完全限定するのは至難の業である。8手目の歩を取っての移動が、苦心の末ひねり出した創作上の妙手。
完成度では現時点で自作中ベスト。全部の駒が目いっぱい働く高密度の手順と思う。
双方角不成もそうだが、初手角をわざわざ成れるところに打って不成で戻るという、ちょっとマニアックな構成が私好みである。
この手順、うまく発展させれば趣向詰になる可能性を秘めていると思う。
前局でも書いたが、本局のような双裸玉が創作物でいられるのは、近い将来、本書のような作品集の記録だけになってしまうはずである。
このような裸玉を含めた簡素形の創作というものは、今後2つの進む道がありうる。
1つは、好作が多く得られそうな条件に絞って絨毯爆撃注5-1 をすること。即ち、その意味で収率の高いよい条件を嗅ぎ付ける能力を問われることになる。この場合はルールが先にあって、手順はそこから必然的に発掘されてくることになる。
もう一つは、創意ある手順を表現する新たなルール、またはルールの組み合わせを案出するかということ。この場合、は表現したい手順が主で、ルールは従である。
その意味で、本作は現時点でのfmの守備範囲の枠を越え、手順を表現するためのルールの創作または組み合わせ、という新たな表現方法の実験作でもあるのだ。
一族におけるfmの代表的な使用方法。太郎作品集その他を参照のこと。
Copyright © KAMINA Family 2001