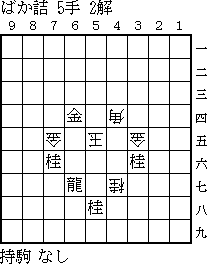
2解ともハートの二段曲詰である。
手数も短く、手順も単純なのだが結構評判が良かったのを覚えている。
当初はこのような形ではなく36桂は玉方で1解目はそれを取って67桂という手順であった。
現在の形を思い付き、再投稿したのだが金、龍の動きに対称性がありこの形で良かったと思う。
ハートの曲詰には、この作品のほかに3段曲詰と私の結婚祝い(未発表)のときに作ったものがある。また、ハート詰にはもう一つネタがあるのだがまだ創作に着手していない。
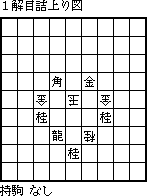
|
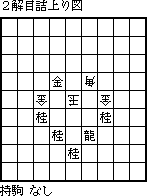
|
二上二上の四段曲詰である。昔の作品はよく知らないが四段曲詰というのはめずらしいのではないだろうか。
以前からかしこ詰で有名な曲詰の作品のヤヒロ印、二上、NHKなどを作りたいと思っていた。なかなか面白い手順が思い浮かばずそのままにしていた。
この作品は大学院時代バイトの帰りに電車の中で数学の問題を解いていたとき閃いた手順である。
当時、詰将棋に対して一生懸命だった時期とはいえ変な時に思い付くものである。
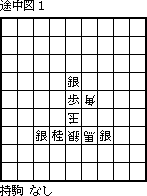
|
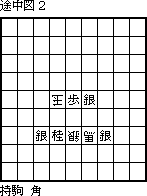
|
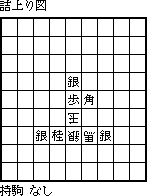
|
6手詰から2手逆算した作品である。
双裸玉**ばか自殺詰で10手以上になると怠け者の私はなかなか解く気にならない。逆に6手以下だと何か物足りなさを感じてしまう。
私が6手詰を作ったときほとんどの場合意地悪をして2手逆算し8手詰にすることにしている。
自殺詰では基本的な逆算方法を行ったのだが意外と簡単に完成してしまった。
この作品は私としてはかなりの自信作であったのだが、解答の短評を読んでみるとそれほどの評価は得られなかったようである。
この詰め上がりはあまり見かけないが、七郎氏の作品に同じような詰め上がりの作品がある。
この作品は他の作品を解いていたときに閃いた手順を図化しようとして、その副産物としてできたものである。
私はよく問題を解いていたときに閃いた手順を図化する方法で作品を作ってきていた。詰パラの作品も解くことが少なくなっているのでこのような閃きで作ることがなくなってきている。
最近は、自分の作品の余詰筋を作品にすることが多い。元々作ろうとしていたものは、できないんだけど・・・
|
[9-4b] 1993年9月 第1回 神無一族の氾濫 神無七郎 |
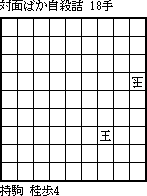
|
私の作品の中に26王→36王の対面ばか自殺詰(8手)の作品(詰パラ98年8月号)がある。その作品は、対面の定番的な詰上の作品で非常につまらないものなのである。
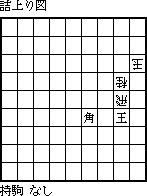
本作品は、一つ王を右に寄せただけの違いなのであるが非常に珍しい詰上の作品になった。次図をご覧頂きたい。
対面特有でこの詰め上がりを想像するのはたやすい事ではないと思う。
私も双裸玉対面ばか自殺詰をかなり作っていて、気にいっている作品もいくつかあるがその中で一つを選べといわれれば間違いなく私はこれを選択する。
序盤の持駒変換、中盤の銀取、終盤の香合からの収束とうまくまとまっていると思う。合駒制限の為だけの配置がない上に駒数も非常に少ない。手数はそれほどの長さではないのだが完成度ではシリーズ中一番かもしれない。
以下、簡単に盤面の遷移をご覧頂きたい。
|
〔1→28手 序盤の持駒変換〕 飛→角→角角→飛角の順で持駒を変換 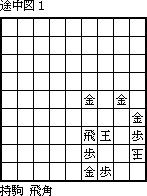 |
〔29→41手 中盤の銀取〕 飛角を使用し、銀を3枚取得 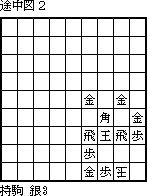 |
|
〔43→60手 終盤の香合からの収束〕 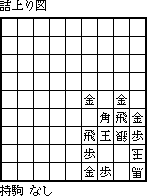
|
私が始めて手にしたパラには、第一回目の神無一族の氾濫が掲載されていた。
ばか、ばか自殺、安南、対面など今まで聞いたこともない言葉が各問題ごとについていた。なんかよく分からないけど解いてみるかと思いルール説明と格闘し解いた記憶がある。
半分ぐらいしか解けなかったと思うがすっかりフェアリーの面白さにはまってしまった。この辺りがちょっと(かなりか?)変なのかなと自分で思ったりする。
その6ヶ月後、第二回神無一族の氾濫が掲載された。このときに三郎氏の『星姫』という密室型の作品があり、この作品を解いたときの衝撃は今でも忘れられない。
|
[9-6b] 1994年6月 第2回 神無一族の氾濫 神無三郎 『星姫』 |
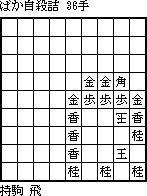
|
この星姫に刺激を受け、4年後完成したのが『なりなり』である。
|
[9-6c] 1998年9月 フェアリーランド 赤木誉幸 『なりなり』 |

|
シリーズ当初の作品なので、囲いの作り方がヘタである。1、6筋の壁が暑苦しい。太郎氏からスッキリとした改図案を頂いたのだが、私の怠慢でこのまま発表してしまった。

|
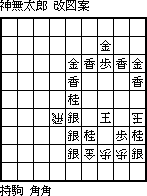
|
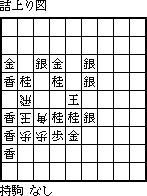
シリーズの中で、私が一番気に入っているのが『なりなり8』である。
中段の密室を作る時のメリットは、成不成の非限定が発生しないようにできることである。下段で密室を作っていたが成不成の非限定が発生した場合は中段に浮かす。
ただし、中段の密室は大模様になってしまう。『なりなり7』がその例である。
また、単に密室の囲いを中段に移動させると飛、角、香などを組みあわせて密室を破られてしまうことが多い。
『なりなり8』は、下段から中段に移動させた作品の中で非常にうまく行った例である。
現在、発表している『なりなり』シリーズの中では最長手数の作品である。
この『なりなり10』のように同じようなことを繰り返しているように見えるが実はほんの少しずつ局面が変化しているというパズルチックな手順の作品が私は好きである。
この作品も飛角歩を使い少しずつ局面を換えながら詰め上がっている。
|
〔1→8手〕 87王→79王、持駒 飛飛→飛  |
〔9→42手〕 持駒 飛→飛歩 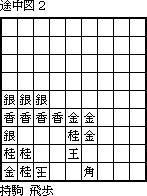 |
|
〔43→60手〕 77歩を追加 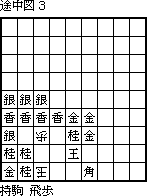 |
〔61→80手〕 77歩→77と、持駒 飛歩→飛飛 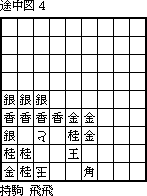 |
|
〔81→92手〕 77と→78と、持駒 飛飛→飛角 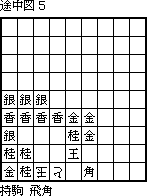 |
〔詰上り〕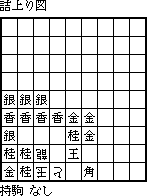 |
この作品は着手の範囲が非常に狭く詰めることはそれほど難しい事ではないと思う。ただし、最短手数で詰ませるのは少しなやましい作品であると思う。
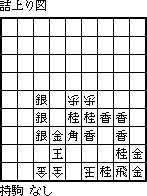
『なりなり12』を作成後、面白いアイデアが浮かばずなりなりシリーズを作るのを一時中断していた。仕事に疲れていた時になんとなく作りたくなって作ったのが『なりなり14』である。これは完成までにえらい苦労したのを覚えている。
37成銀を見て頂ければ、苦労の跡が伺えると思う。
始めはあまり見るべきところが無い作品だと思い、発表するのを控えようとしていたが、OFMで37に銀を忍ばせる手順や57へ金鋸で移動する手順を褒めて頂いた。
99年最後の神無一族の氾濫で(ただの手数順だけど)トリを勤めた作品である。
Copyright © KAMINA Family 2001