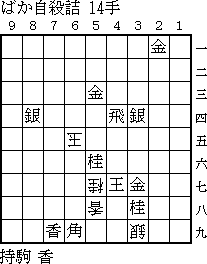
究極の7種合。これ以上短いものは考えられません。
創作過程には、まず『白雪姫』(打歩ばか詰33手7種合 ― 後述)の存在があります。更にこの序の感じを借りて、作りあげたのが『不思議姫』(ばか自殺詰 20手7種合 1995年6月 ofm060)。そのとき、究極の手数は14手であり、できるだけこの究極の手数に近づけたものを作ってみようと決意しました。
詰め上がりはいちょう返し(王手した駒がピンされており、相手に逆王手された瞬間詰んでしまう詰め上がり)しか考えられません。これから逆算を開始、意外と簡単にプロトタイプは完成したように思います。(44飛の配置がポイント)
当初は初手に角で香を取るむき出し手順でしたが、七郎さんから角を飛び出す手が成立する可能性を提出され、悪戦苦闘が始まりました。
歩以外の駒はそれぞれ一枚ずつ残して盤上に配置しなくてはならず、逆に歩は配置したくないのです。何度図をつくって壊していったことか。速いパソコンとfmを使って一族総がかりで検討してくれたことを有り難く思います。(確か3週間近くかかったと記憶しております)
*
この作品の価値は七郎さんにしっかりと評価していただいておりますが、本当の評価は歴史がしてくれると思っています。
構想の伏線は25年以上前。京大将棋部のボックスにあった一冊の詰将棋パラダイス。ぱらぱらとめくっていたら、加藤徹氏の詰将棋が目に止まりました。身動きできない玉のまわりから飛角を打って徐々に局面を変化させていって、詰ます構想を当時とても新鮮に思えました。この構想を何とかばか詰系で実現できないかと試みましたが、どうもばか詰ではうまくいかず、長い間ボツになっていました。
10年程前、長野にいたとき、打歩ばか詰でやれば何とかうまくいくのではないか、とふと思いつき、いろいろためしたところ100手前後の図が得られました。菊田くんが家を尋ねてきたときに図を見せてみましたが、反応は今一つ。しかも、終盤致命的な手順前後が生じており、またまたお蔵入りとなりました。
さて、fmが打歩ばか詰をサポートして、太郎さんが密室型ばか自殺詰の傑作をものにしたある日、氾濫に投稿する作品が何かないかな、とまさぐっていた時、この過去の図を発見しました。図を眺めているうちに回転の方向をひとつにすることと余詰を解消することをいっぺんに解決する妙案が浮かびました。それは玉のこびんに駒を配置することで(決定図では27歩)、歩や桂馬などいろいろの配置を考えてみました。この妙案によって130手近い完全作が得られました。
これを決定図としてもよかったのですが、更に成桂、成香らの最適の配置を探っていくつもの図をためしていたところ、偶然今までの回転とは違う破調の手(130手目のと金と成桂の入れ替え)を発見しました。これで少し謎解きらしくなり、作品になってきました。これで150手台になりました。
その後、金の特性を生かした(後ろ斜めからの王手がかからない)龍馬、龍王、成香のはがしが入り、太郎さんの傑作の手数を手数だけでも超えて満足いく仕上がりとなりました。決定図には太郎さんのアドバイスをいただき、7×6の桝にコンパクトに収まり、七郎さんにも評価していだきました。
図に成駒がふんだんに配置してあるのは、ひとつには成桂、成香がポイントであることをカムフラージュするためであり、もうひとつには解答をかきやすくするため他意はありません。
よい刺激をも含めて、この作品の創作に対する一族のみなさんの多大なるご協力に感謝するとともに、何年も粘ればこういった作品もできるというひとつの証明ではないかとつらつら書き綴った次第です。
かしこ以外では初の7種合です。
まず、歩香桂の3連合を軸につくり始めました。桂馬は2段目には合駒できないのと、歩は同じ筋には合駒できないの枷を使って歩香桂の合駒の順を限定してみました。(56と75歩がその限定の駒です)
次に飛や金といった駒は強大なので、最後に登場させることとし収束をつくりました。84飛87桂95歩75歩といった配置がポイントです。
最後に序の部分をつくりました。銀合がなかなかできずに苦戦しました。わたしは詰将棋の作り初めのときは、銀を使うのが得意ではなかったようです。(このごろは、そうでもありませんが)特にばか詰系の場合、歩や桂馬(いちばん使いやすい)や香車と角が使いやすく、銀がいちばん使いにくい感じがします。
さて。
fmでの検討はできなかったので、余詰が発生してサロンで修正しました。
サロンでの修正ついでに、普通詰の順列7種合を取り出しておきます。現時点での順列7種合では最短のはずです。
|
[3-3b] 1980年5月 デパート 小林看空 『天使』 1996年10月 読者サロンで修正 |
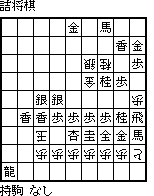
|
カピタンの出発点は衝立詰でした。記念すべき第1号の第1ページは衝立将棋の指方!でしたし、第1号2号4号の詰将棋コーナーはすべて衝立詰でした。
衝立将棋は若島さんがチェスから持ち込んだと記憶しています。確か関西の奨励会でも指されていたんじゃないかな。
チョンボは8回までといったルールも実戦の中から固まっていったもの。
さて、作品の解説。
何とか裸玉をつくろうと思い立ち、当初は11玉で持駒も飛飛金金金銀、あるいは飛飛金銀銀銀だったと記憶していますが、それは余詰などがあり、加藤徹氏のアドバイスで飛飛金金銀銀に決定、その後21玉でも同一手順が成立するということで発表図になったわけです。
まあ、持駒も整って、幸運が重なったわけです。
合駒の種類が最後まで判らない(ただし、飛車ではない)というのも衝立詰ならではと思っています。
衝立将棋のルールは普通の将棋と同じです。しかし、相手の指し手はわかりません。
審判がいて、次のことを1手指すごとに対局者へ教えてくれます。〔( )内は審判の行為〕
| a. 自分の手番 b. 相手の手番 | ||
| 1a. 相手の駒を取った場合 | (取った駒を渡してくれる) | |
| 1b. 自分の駒が取られた場合 | (盤上から取られた駒がなくなる) | |
| 2a. 王手をかけた場合 | (王手です)、という声が聞こえる | |
| 2b. 王手をかけられた場合 | (王手です)、といわれる | |
| 3a. 指し手が反則の場合 | (チョンボ*回です)、といわれる チョンボ9回の場合は反則負け | |
| 3b. 指し手が反則の場合 | (チョンボ*回です)、という声が聞こえる チョンボ9回の場合は反則勝ち | |
| 4a. 詰めた場合 | (詰みです)、という声が聞こえる | |
| 4b. 詰められた場合 | (詰みです)、といわれる |
上記以外は審判は相手に指したことを告げ、指し手をうながします。
反則は1局に8回許されますが、9回反則をしてしまいますと、チョンボ負け(反則負け)となります。
注: 反則=チョンボ、の指し手は次のような場合です。
など。
衝立詰将棋は文字通り衝立将棋の詰将棋ですが、初期局面はわかっているとして進めます。(ここが実戦とは違う点です)3手目の22金のようにわざとチョンボしてみるのもテクニックのひとつです。
一族の世紀末作戦のひとつに、小林看空詰パラ復活作戦というものがありました。太郎さんによれば小林看空の詰パラの登場回数はすでに90回は超えていて、何とか100回に到達してフェアリー同人に仕立てるという構想でありました。
で、当然投稿する作品がないと困るので、こつこつと駄作を作り出したのでした。
最初の作戦では、ばか千日手や先手取禁ばか詰が候補でいろいろと作ったのですが、そのうちに新テーマで何か作りたくなって、7連合をばか詰で実現できたらと考え至りました。さすがに縦横斜めと簡単に出来ました。最初は投稿するにはこんなものでもいいだろうと思っていたのですが、そのうちに欲が出て、ダブル7連合といったものはできないかな、考えました。しかし単なる7連合は最後の合駒を取って同Xとすればいいのに対して、ダブル7連合は玉方で同Xというわけにはいきません。つまり合駒を要求した駒を同Xと取られ、2回目にはその駒を合駒されて簡単に詰んでしまうのです。これには参りました。一見不可能です、これは。
そのうちに縦横斜めとつくった一局に香車を使って成らずと入り手を繋げる可能性を見出したのでした。2回目に7連合を要求する駒の可能性としては飛車しかなく、それも龍で敵陣からです。結局1回目は1筋で香車による7連合、2回目は9筋で龍による7連合となったわけですが、9筋で最後の駒を取ったあと99に歩を打って追っていくわけですが、9筋には駒を置けず、何度不可能じゃないかなと思ったことでしょうか。ようやく、83と63に桂を配置できて何とか解決、不可能ではないことが証明されたわけで、これが大きな一歩でした。
こういった創作はfmはほとんど検討役で、いくつもの可能性のある図を何百何千図と検討するわけにはいかず、茨の道なのです。
この作が『真夏の夜の夢』でダブル7連合の1号局となりました。
少し気分を替えて、いつもの『○○姫』といった命名ではなく、真夏の暑いときに出来た夢の作ということで名づけたのです。
12月号の氾濫の出題なのに、『真夏』ではミスマッチなのでは、と七郎さんに言われましたが、そういった事情なのです。
さて、一旦不可能が可能になると事情と言いますか、心の持ちようが変化してきます。太郎さんが『真夏の夜の夢』の後を受けて、Kマドラシばか自殺詰でダブル7連合の可能性を探った図を提示されました。この作品は惜しくもダブル7連合にはならなかったのですが、龍と飛車が上からと横から王手するものでした。
この図からピンとくるものがあって、もしかしたらダブル7連合は飛車の横利きを利用したらうまくいくのではないか、と思いさっそく創作に取り掛かりました。
玉を9筋に置いて、1筋から飛車の王手、そして玉は八段目を横這いして、1筋に至り、また9筋から飛車の王手というストーリーを仕立てました。そのとき、もしかしたら、一回使った飛車をもう一回使えるのではないかという虫のいい考え方をしたところこれがまたうまく行きました。どうやら虫のいい手順を思いつくのが創作の秘訣のようです。9筋で桂合を絡ませて飛車筋をずらしたり、王の配置、31角の配置はテクニックとして、一番苦労したのは、五段目〜七段目の配置で、収束と併せて56金と57桂の宙ぶらりんの配置で何とか作品にできたのでした。創作時間としてはほぼ1日と極めて短いものでしたが、集中できたのと、これだけの経験がものをいったのでした。
何事も経験ですかね。
命名は最初『熱気球』としましたが、飛車の動きが主体なので『飛行船』に変更、加えて、飛車の動きを印象づけるため、18飛車を配置して決定図としました。
後は角を含めたダブル7連合が課題ですが、かしこ詰における7連合が未だないように不可能に近いのかな、と思いつつ。。
さて、復活作戦はどうなったかといえば、好作をつくってしまったので、現時点では何も投稿していないのです。
|
[3-5b] 1999年12月 第12回神無一族の氾濫 神無三郎 『真夏の夜の夢』 |
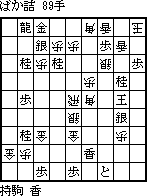
|
発想の出発点は最後の2手であって、そこからの逆算が全てです。
11角打が限定である以上、玉、王、銀の配置は必然自然、また香合を限定にするためにもう1枚の飛(1枚は持駒!)をどこかに配置しておく必要がありました。で、14龍の配置は必然。4手では面白くないので、22と→23と同角の逆算を試みました。22との配置は他の配置では11角からの余詰があるのでこれもまた必然。
当初の角の配置は45角で加藤徹氏につぶされて56角の修正となり、これも必然。必然がいくつも重なって決定図となりました。
飛角が手駒にあるのに初手からの駒捨て(と金なのですが)は指しにくかったようです。また両王手をにらんだ最終2手も指し難く、難解作に仕上がったようです。無駄な配置もなく、余詰もなく、今思えばうまくいったものです。
おまけとして、同号に載った手数手順探しの問題を2つ示しておきます。それぞれ1ヶ所小キズがあります。これを解くには手の方が断然早い!
|
[3-6b] 1981年4月 カピタン23号 小林看空出題 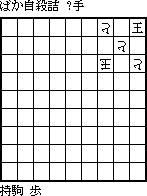
|
[3-6c] 1981年4月 カピタン23号 小林看空出題 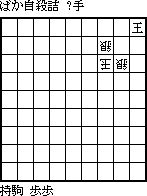
|
この当時何作もクイーンばか詰をつくりました。どうも自分は同じテーマをいくつか試みないと気が済まないようです。
結婚したばかりの正月、かみさんの家に行って、お屠蘇などを飲みながら、紙と鉛筆と消しゴムを持ってひたすらクイーンばか詰をつくっていて、かみさんの父親に呆れられました。
クイーンばか詰はクイーンが強いので、なかなか余詰がでません。構想さえしっかりしておれば、意外とつくり易い気がします。
この作品以外にも取り上げたい作品が多々あるのですが、王がある作品はfmのチェックが入っていないので、今回はこの作品にしています。
テーマは王手をかけている駒ではなく、他の駒で合駒を取るという単純なもの。しかし、盤上の駒が2枚とシンプルな上に、初手から銀を打って舞台からまず作らなくてはならないのでやりづらいかったようです。香車の限定打に飛車合が綺麗に入り、まずは満足です。ただ、クイーンの動きが少し地味なので、派手な動きを期待された人には肩透かしだったかな。
口直しにクイーンが飛び回る作品を掲げておきますので、お楽しみください。
|
[3-7b] 1986年9月 カピタン34号 小林看空 |
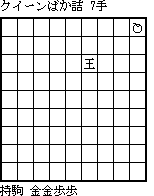
|
ホラータッチで書いてみます。。
『白雪姫』にはひとつの恐ろしい伝説があります。
それは、この作品を載せたミニコミ誌は、解答発表号を待たずして眠ってしまうという編集者にとって実に実に恐ろしい伝説なのです。あたかもグリム童話における毒の林檎のような作品なのです。
その犠牲になったミニコミ誌を主宰されていたのが、右京さん(将棋パズル)と六郎さん(将)だったのは更に心の痛む思いです。
第3回目に載ったのがOFM。当時主宰されていた太郎さんはわざわざ掲載する前号(ofm023)で『白雪姫』を載せる予告のお祓いをしてこの呪いを封じ込めたものでした。
第4回目は詰パラ。この時は太郎さんが不要な駒2枚を発見され、少しスリムになった『白雪姫』として登場して、つつがなきを得ています。
さて第5回目。もしかしたら、その呪いが復活し、襲いかかるのは、これを読んでいるあなた自身かもしれません。。
伝説はともあれ、三郎にとって第3作目にあたる7種合でした。
| 第1作 | かしこ詰 | 『天使』 | ||
| 第2作 | ばか詰 | 『橋姫』 | ||
| 第3作 | 打歩ばか詰 | 『白雪姫』 | 本作 | |
| 第4作 | ばか自殺詰 | 『不思議姫』 | ||
| 第5作 | ばか自殺詰 | 『謎姫』 |
7種合作は余詰修正などそれぞれ数奇な運命をたどっております。
最初の発表図がそのまま、というのは今の所『不思議姫』と『謎姫』だけです。
もっとも、『謎姫』は『不思議姫』が進化した図なので、実質的には『謎姫』のみです。
発想の原点は序の4種合です。ちょっと形を変えれば5種合は簡単に実現できる。これは打歩ばか系に特有の感覚ではないでしょうか。歩を入手するには角の入手が絶対なのですが、その前にもう一仕事しておく必要があります。即ち銀合の出現で、創作的に言えば、銀と角との合駒の区別に苦労することになります。『白雪姫』においては角を相手側に渡す時期を銀の入手のあとに設定することで解決しました。55銀とする時期を限定するために75王と45飛の配置は心苦しい限りですが、打歩ばか詰ではしばしば出現する、玉が動けないという自由度の少ない開放的密室型なので仕方ないところです。
7種合を終えた後の32手目は金の移動合なので、統一を欠いたイメージですが、おまけか夾雑物ということで、打歩ルール自体にはかかってこないと思います。
打歩ばか詰は将棋パズルで発生したルールで、最初パラには遠慮して投稿しませんでした。最終手が打歩詰指定ですので、かなり思い切ったことができます。
さて、次図はやさしい打歩ばか詰ですので、詰めてみてください。
|
[3-8b] 1999年6月 第11回神無一族の氾濫 神無三郎 『青姫』 |
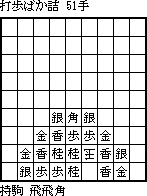
|
密室の玉を追い回すばか自殺詰を作りたくてこね回したのがこの作品です。今でこそ、太郎さんの170手の傑作がありますが、当時は20手越えでさえ希でした。
『風の砦』の命名は岡谷市(実家のある)の原頭と山中につくられた「やまびこ公園」内にある砦から。当時は命名してありませんでした。
ちょうど30手目で前半と後半に分かれます。つくり方も前半と後半に分けてつくりました。壁をつくるための飛角、特に桂香がぜんぜん足りなくて困りました。54角45歩といった配置が苦心の跡。
fmの検討の結果、完全であることが確認(速いパソコンならば数分!)されたこともあって、ひとつのマイルストーンとしてここに掲げます。
もうひとつのマイルストーンは、箱男名義の前衛賞授賞の作。成生の非限定がありますので、作品集には採りませんでした。ともあれ、当時は大らかでした。
|
[3-9b] 1984年6月 フェアリーランド 箱男 第11回前衛賞短編賞受賞 |
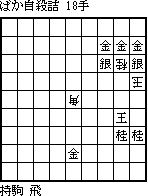
|
ばか系においては、玉方の妙手は不成ではなく、成である、という名言があります。では、ばか詰で玉方の6種成を何とか実現してみようということで、まずは飛車と角の成を中心につくりはじめました。収束ができたとき何とかモノになるのではないかと思い初めましたが、それからがイバラの道。順列にこだわらなければすぐに何とかなったかもしれませんが、当時はfmは存在してなく、何度も何度も花沢先生とハガキのやり取りをしたものの、余詰の嵐。修正不能で御蔵入りしていました。
fmの出現とともにようやくまた取り組む気持ちが起こり、65王を配置して不満ながら何とか銀成を限定して順列6種成『時姫』を仕上げました。fmがなければ到底つくりあげることができなかったでしょう。
ofm029に載ったときは31手だったのですが、太郎さんのアドバイスにより2手短くなりました。
花沢先生、太郎さん、そしてfm開発者の次郎さんに感謝感謝です。
どうもわたしは、条件作が好きなようです。参考作品は、周辺巡り2回転の条件作。難易は二の次です。
|
[3-10b] 2000年6月 第13回神無一族の氾濫 神無三郎 『かごめかごめ』 |
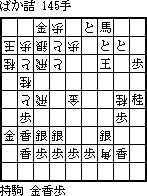
|
まず当時(ofm047-11)の解説をそのまま掲げておきます。
興奮がそのまま伝わってくるでしょう。
▼神無三郎
◆背面キルケばか自殺詰4手のベスト。
本作を見つけた瞬間は何が何だか分からなかったが、分析するに従っておこり病のように、本作のすばらしさが伝わってきてがたがたと震えた。
どうか、自分自身で分析して本作のすばらしさを味わってほしい。
◆98王が99ならば043-2に還元して持駒金1枚で済むのだが。。
◆本作は4手ながら詰めあがりに向けて複雑な手順を採る。
初手は斜め背後から角の直打ちからはじまる。
2手目は逆王手の香車打ち。(なぜ香車なのか最終手を分析しないと分からない。)
3手目も逆王手の金打ち。
そして狙いすました、最終手の角打ち。
王で取れば043-2と同じ「ゴースト」の狙いだが、本作の恐ろしいのはその先にある。
この角打ちの王手を外すにはもうひとつの道がある。
それは、87の金を角の機能を利用して(背面ルールである)どこかにとばすのだ。左対角線の動きは76の香車がピンしいるのでダメなので結局76金と香車を取るしか手段がないことを確認していただきたい。しかし、この手も王手解除にならないのだ!その瞬間香車が91の地点に復活して(変形「転生返し」)98の王を抜かれてしまうのだ!
つまるところ王手を解除する手段がないので「詰め上がり」である。
◆戻って初手の角打ちがこれ以上遠いと76金が成立して詰みとはいえなくなる。
角の短打は無理矢理香車を金に取らせる意味だったのであり、2手目は香車打ちでなければならなかったのである。
◆加えて本作は「いちょう返し」でもあり、「ゴースト」「転生返し」もそろった傑作であることは間違いない。
さて、用語解説。
「いちょう返し」とは、逆王手返しのこと。白土三平氏の忍者漫画から引用しました。すでに『謎姫』などで有名ですね。
「ゴースト」はいわゆる「影の足」で、キルケで元の位置に戻ることで紐がついていることです。この場合は98王で88角を取ろうとしても、取った瞬間キルケルールで角が22に戻るため、結局は王で取れない状態です。
「転生(てんしょう)返し」とは87金で76香車を取ろうとすると、取った瞬間香車が91に復活して王手となり、結局は取れない状態です。
フェアリーもチェスのように手筋の命名が欲しいですね。
理論を発見したらまず命名せよ、と人はいっております。
これからが真の解説。
fmが本格的になって、パソコンの解析速度も速くなってきて、双裸玉の全検が現実になってきつつあったあるとき、七郎さんから対面キルケばか自殺詰4手および背面キルケばか自殺詰4手の全検の提案がありました。
それまでは、おいしそうなところをぽつりぽつりと摘まんでいましたが、自分の遅いパソコンでも4手なら何とか全検できそうでしたので、さっそくパソコンにかけてみました。全検なので持駒1枚ではなく、持駒2枚まで、また盤面の王と玉の配置も、キルケなので飛角の復活の位置が違うということで、対称の位置関係のものも全て検討したので、30万通り位の数字になったと記憶します。しかし、さすがパソコン、思いの外短時間で全検ができましたが、そのあとが大変。完全作を一作ずつノートに書き写し、分析に取り掛かりました。ただ分析するだけでは面白くないので、いろいろの手筋を抽出命名しながらコメントを書きつつOFMに投稿したのです。
その中でのピカ一の一局がこの局で、たった4手なのに分析すればするほど味わい深い局でこの一局を発掘しただけでも全検した価値はあると思います。
双裸玉は持駒1枚の場合の全検が進んでおりますが、完全作は少ないにしても2枚や3枚(それ以上)でも逆にそのようなものは、結構深みのある局が得られるように思えます。
今後の研究が楽しみです。
キルケルールはそれ自体左右対称でない(大駒の復活する場所が限定されているので)という面白い特性を持っていますが、他のルールと組み合わせることによって、更に面白くなります。
マドラシルールと安南ルールを組合せた例を示しておきます。
|
[3-11b] 1994年9月 Online Fairy Mate 031号 神無三郎 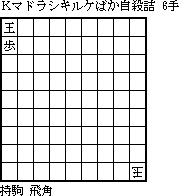
|
[3-11c] 1994年9月 Online Fairy Mate 031号 神無三郎 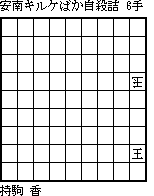
|
炮=パオ
動くときは飛車と同じ。駒を取るときは必ず一つ駒を飛び越えて取る。
飛び越える駒は敵味方どちらでもよい。グラスホッパーと違って、着地場所は飛び越えた駒の隣でなくてもよい。
成ることはできない。特に記述しない限り受方の持駒に炮はない。
炮という魅力的な駒に取り組んだときのひとつの成果です。
このとき、将棋パズル(田宮克哉さんが主宰されていて、その後右京さんが引き継がれていたミニコミ誌 ― 現在休眠中)に「看空館〜炮のある風景」として十局近くいっぺんに掲載された生き残りの1局です。(殆んどがつぶれた! ― もう1局生き残った作は、1×9盤で詰方12歩、受方15炮、持駒香の打歩ばか炮詰11手です。右京>盤面をフルに使った好局ですので挑戦してみて下さい。)
余詰が今まだ発見されていないのですが、fmによる全検はされていないので十分その恐れはあります。
炮は中国将棋の駒のひとつで、動き方と取り方が一致しないという面白い駒で、しかも強力な駒です。
大学のときに留学生と中国将棋を指していて、一発で詰まされたのがこの駒でした。
「炮のある風景」というタイトルは、コロンボの「祝砲の挽歌」からイメージを拝借してみました。
さて。
作意は、38飛の発生〜32飛成という炮の利きはずしを軸に構成してみました。27玉は絶対の配置で、六段目より上だと炮の打ち場所が非限定になってしまうし、七八段目ですと角の発生ができないのです。歩の王手に続いて打った歩を影にした炮の王手→飛車の発生→歩を突き出して今度は飛車を影にした炮の王手→王を縛る飛車成→そして狙い澄ました香車打(香車を影にした炮の王手)→角打によるブロックと詰め上がり。
香車の打つ位置は他の打ち場所ですと香車が最終手に対して移動できるので限定です。
炮がテーマで、しかも盤面を大きく使っていて気持ちがよいと自負しております。何局もつくってみるとだんだんとテーマに馴染んだ手順構想が湧いて来るようです。一発でテーマに合った局をつくれる天才もいますが、われわれ凡人群では、何度も何度も同じテーマを繰り返し繰り返し取り組んでいるうちに育まれるものと思います。
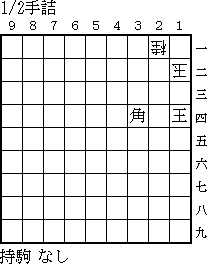
この作品はユーモアとエスプリを楽しむ作品なので、解答は省略させていただきます。お楽しみください。
発端は、文芸雑誌「すばる」1984.09号に載った柳瀬尚紀さんの次の作品。
柳瀬さんは、タイム誌で1900年代でベストとされるUlyssesの作者James Joyceの翻訳不能とされた作品Finnegans Wakeを訳されて話題になりました。
|
[3-13b] 1984年9月 すばる 柳瀬尚紀 |
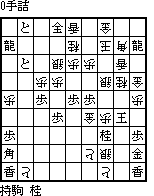
|
チェスでは、サムロイドの作品に1/2手詰というのがありまして、それはキャスリングとアン・パッサンが絡んでいるのですが、0手詰というのは、有り得ない、反則負けだのわいわいがやがや。
一応自作はフェアプレイのつもりです。
また、それに続く作品群のうち傑作と思われる4作を示しておきます。
これらも解答はつけておきません。
どうしても解らない方はカピタンのバックナンバーを捜していただくか、わたしにお問い合わせ願います。ただし柳瀬さんの作品に限っては、わたしも作意は知っておりませんので、問い合わせされても応じかねますが。。
ヒントはどうやら先手持駒なし後手持駒桂にあるらしいのですが。。
|
[3-13c] 1988年5月 カピタン39号 花沢正純 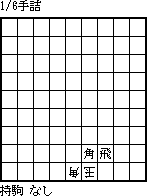
|
[3-13e] 1988年5月 カピタン39号 小林看空 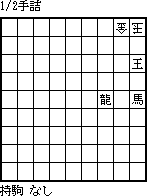
| |
|
[3-13d] 1989年7月 カピタン40号 山本昭一 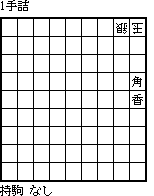
|
[3-13f] 1989年7月 カピタン40号 若島正 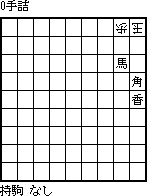
|
Copyright © KAMINA Family 2001